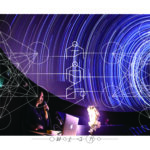芥川龍之介とセオ・ブレックマンの出会い。これだけで胸が高なり、私は会場へと急いだ。
■文 / 原田和典
小説家・芥川龍之介の作品を題材にした新作オペラ『note to a friend』の日本初演が、2月4日と5日の2日間にわたって東京文化会館で行なわれた。これはニューヨークのジャパン・ソサエティーと東京文化会館の国際共同制作による第2弾(第1弾は、2017年秋に上演。夏目漱石の『夢十夜』が原作のオペラ作品)。16歳の頃から芥川のファンである作曲家のデヴィッド・ラングが、芥川の『或旧友へ送る手記』、『点鬼簿』、『薮の中』を読み込み、ラング自身の言葉によって「死」の世界を作り上げた。
オペラは9曲で構成されており、編成は男性ヴォーカルひとりと弦楽四重奏というシンプルなもの。冥界からやってきた「死んだ男」が主人公となり、友人(聞き役の俳優:サイラス・モシュレフィ)に自らの自殺、そして家族の死について語っていく。「死んだ男」はジャズ・ヴォーカリストで作曲家のセオ・ブレックマンが表現する。セオとラングは30年来の付き合いであるという。

物語は「people who kill themselves don’t usually tell you what they think about killing themselves(自殺する人は自殺についてどう考えているのか、ふつうは教えてくれない)」と言うセリフから始まる。セオは、重いテーマを大げさに語るわけでも押し付けるわけでもなく、自然に語り、歌う。私は、ギター奏者のベン・モンダーとのデュオ、トランペット奏者のアンブローズ・アキンムシーレとの共演など、いろいろなところで彼の歌を聴いてきたが、ここまで柔らかく、子音の美しい“声の使い手”だったとは、と、いまさらながら目の覚める思いがした。弦楽も始終彼の表現に寄り添っていくようで、友人(サイラス)も静かに主人公(セオ)の言葉に耳を傾けている。
誰かが近づいてきたのが分かっても、闇がすべてを埋め尽くしてしまったあとでは遅すぎたのだ—–そう綴られる最終章「long silence(長き沈黙)」、そして最後のセリフは、「I was already gone I had found what I was looking for and I was gone(私はもういない 探していたものを見つけた そして私はいなくなった)」。弦楽器が短い音を強く素早く2度かき鳴らすと、舞台が真っ暗になった。
しんと静まりかえる会場に、次々と我に返った人々の拍手が響く。我々の耳と目は1時間にわたるラングの世界に誘い込まれ、気づかぬうちに「死」を体験していたのだろうか。神秘的で説明し難い感覚、それは大きな余韻となって私を包んだ。